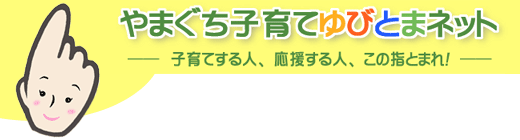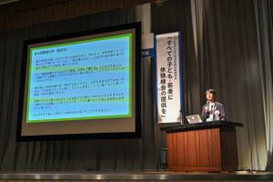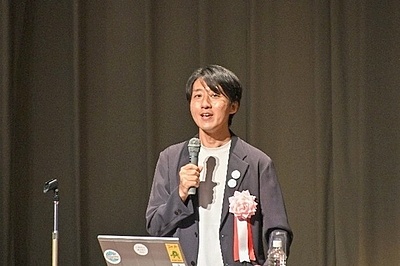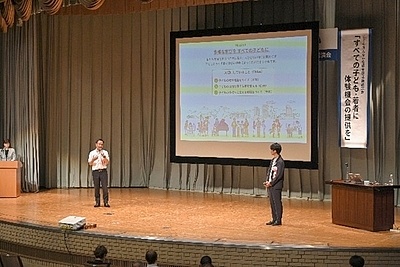|
|
|
令和7年度少年の主張コンクール発表作文紹介(優良賞)
2025/10/03
「小さな行動がつくる未来」
周南市立太華中学校 2年 舩越 煌莉
私は毎朝、学校へ向かう途中に近くの川沿いを歩きます。季節によって変わる風景や鳥のさえずりが好きで、この道は、私にとって特別な時間を与えてくれる場所です。しかしある日、川の岸辺に空き缶やビニール袋が散らばっているのを見つけました。風に飛ばされたゴミが川に入って流れていくのを見て、私は胸が痛くなりました。その光景は、私の心に深く残りました。
その日から、私は環境についてもっと真剣に考えるようになりました。学校の図書室で環境問題に関する本を借りて読んだり、ニュースやドキュメンタリー番組を見たりするうちに、私たちが暮らす地球が今、危機に直面していることを知りました。気候変動による異常気象、森林の伐採、生き物の絶滅、海洋プラスチック汚染、これらの問題は決して遠い国の出来事ではなく、私たち一人ひとりの生活とつながっているのです。
たとえば、毎日飲んでいるペットボトルの飲み物やコンビニのお弁当、便利な暮らしの中で、私たちは大量のプラスチックごみを出しています。世界では毎年約800万トンものプラスチックが海に流れ込み、ウミガメや魚など多くの海の生き物が命を落としていると知ったとき、私は言葉を失いました。このままでは、私たちの未来はどうなってしまうのだろう、と不安にもなりました。
でも、ただ「こわい」「ひどい」と思って終わるのではなく、「じゃあ自分にできることは何か」を考えることが大事だと感じました。私はまず、マイボトルを持ち歩くことにしました。最初は少し面倒だと思っていたけれど、今ではそれが当たり前になり、むしろ誇らしく思えます。お気に入りのデザインのボトルを持つことで、楽しい気持ちにもなれました。また、家では家族と一緒にごみの分別を見直したり、使い捨てを減らす工夫をしたりしています。ラップを使わずに保存容器に入れたり、ティッシュの代わりに布のハンカチを使ったりと、小さなことの積み重ねです。こうした行動は目に見える変化をすぐに感じられるわけではありませんが、私にはとても意味のあることだと思います。
私がやっていることは本当に小さなことです。でも、もし同じように考え、行動する人が日本中、世界中に広がったら、それは大きな力になります。私は、未来をよりよいものにするためには、一人ひとりの「気づき」と「行動」が何よりも大切だと信じています。
そして、もう一つ大事なのは、「学び、伝えること」だと思います。私たちは、環境についてもっと知る必要があります。なぜ気温が上がるのか、どうすればごみを減らせるのか、再生可能エネルギーって何なのか。学校でもっとこうしたことを学び、意見を交わす機会があれば、自分たちの未来を自分たちで考える力が育つと思います。また、子どもたちの声を社会に届ける方法も増やしてほしいです。私たちは選挙に参加することはできませんが、意見を持ち、行動することはできます。たとえば、地域で行われている環境保全のボランティア活動に参加することや、学校で環境新聞をつくって発信することなど、できることはたくさんあるはずです。
私は先日、学校の友達と一緒に、通学路の落ち葉を拾ったり、ゴミを集めたりしました。最初は「ちょっと面倒かも」と感じていたけど、実際にやってみると「思ったより楽しかった」「もっときれいにしたい」という気持ちに変わりました。自分たちの手で地域をきれいにすることには、大きな意味があります。それは、自分たちの住む場所への誇りや愛情を育てることにもつながるのだと感じました。
こうした経験を通して、「やってみることの大切さ」を学びました。行動しなければ何も変わりませんが、行動すれば、自分自身の考え方や周りとの関わりも少しずつ変わっていくのだと思いました。
私が将来大人になったとき、今よりももっと環境に優しい社会になっていてほしいと思います。そのためには、今の私たちの行動がとても重要です。「どうせ一人の力じゃ何も変わらない」と思う人もいるかもしれません。でも、私はそうは思いません。一人の行動が周りの誰かを変えるかもしれない。そして、その誰かがまた別の誰かに影響を与える。そうやってつながっていけば、きっと社会も世界も少しずつ変わっていくはずです。
私たちの未来は、まだ白紙の状態です。そこにどんな絵を描くのかは、私たち次第です。私は、地球や人、動物が共に生きる優しい未来を描きたい。そのために、小さな一歩を大切に、これからも学び、考え、行動していきたいと思います。だから私はこれからも、身の回りの自然や生き物に目を向け、小さなことでも行動を続けていきたいです。一歩ずつでも前に進めば、未来はきっと変わります。
周南市立太華中学校 2年 舩越 煌莉
私は毎朝、学校へ向かう途中に近くの川沿いを歩きます。季節によって変わる風景や鳥のさえずりが好きで、この道は、私にとって特別な時間を与えてくれる場所です。しかしある日、川の岸辺に空き缶やビニール袋が散らばっているのを見つけました。風に飛ばされたゴミが川に入って流れていくのを見て、私は胸が痛くなりました。その光景は、私の心に深く残りました。
その日から、私は環境についてもっと真剣に考えるようになりました。学校の図書室で環境問題に関する本を借りて読んだり、ニュースやドキュメンタリー番組を見たりするうちに、私たちが暮らす地球が今、危機に直面していることを知りました。気候変動による異常気象、森林の伐採、生き物の絶滅、海洋プラスチック汚染、これらの問題は決して遠い国の出来事ではなく、私たち一人ひとりの生活とつながっているのです。
たとえば、毎日飲んでいるペットボトルの飲み物やコンビニのお弁当、便利な暮らしの中で、私たちは大量のプラスチックごみを出しています。世界では毎年約800万トンものプラスチックが海に流れ込み、ウミガメや魚など多くの海の生き物が命を落としていると知ったとき、私は言葉を失いました。このままでは、私たちの未来はどうなってしまうのだろう、と不安にもなりました。
でも、ただ「こわい」「ひどい」と思って終わるのではなく、「じゃあ自分にできることは何か」を考えることが大事だと感じました。私はまず、マイボトルを持ち歩くことにしました。最初は少し面倒だと思っていたけれど、今ではそれが当たり前になり、むしろ誇らしく思えます。お気に入りのデザインのボトルを持つことで、楽しい気持ちにもなれました。また、家では家族と一緒にごみの分別を見直したり、使い捨てを減らす工夫をしたりしています。ラップを使わずに保存容器に入れたり、ティッシュの代わりに布のハンカチを使ったりと、小さなことの積み重ねです。こうした行動は目に見える変化をすぐに感じられるわけではありませんが、私にはとても意味のあることだと思います。
私がやっていることは本当に小さなことです。でも、もし同じように考え、行動する人が日本中、世界中に広がったら、それは大きな力になります。私は、未来をよりよいものにするためには、一人ひとりの「気づき」と「行動」が何よりも大切だと信じています。
そして、もう一つ大事なのは、「学び、伝えること」だと思います。私たちは、環境についてもっと知る必要があります。なぜ気温が上がるのか、どうすればごみを減らせるのか、再生可能エネルギーって何なのか。学校でもっとこうしたことを学び、意見を交わす機会があれば、自分たちの未来を自分たちで考える力が育つと思います。また、子どもたちの声を社会に届ける方法も増やしてほしいです。私たちは選挙に参加することはできませんが、意見を持ち、行動することはできます。たとえば、地域で行われている環境保全のボランティア活動に参加することや、学校で環境新聞をつくって発信することなど、できることはたくさんあるはずです。
私は先日、学校の友達と一緒に、通学路の落ち葉を拾ったり、ゴミを集めたりしました。最初は「ちょっと面倒かも」と感じていたけど、実際にやってみると「思ったより楽しかった」「もっときれいにしたい」という気持ちに変わりました。自分たちの手で地域をきれいにすることには、大きな意味があります。それは、自分たちの住む場所への誇りや愛情を育てることにもつながるのだと感じました。
こうした経験を通して、「やってみることの大切さ」を学びました。行動しなければ何も変わりませんが、行動すれば、自分自身の考え方や周りとの関わりも少しずつ変わっていくのだと思いました。
私が将来大人になったとき、今よりももっと環境に優しい社会になっていてほしいと思います。そのためには、今の私たちの行動がとても重要です。「どうせ一人の力じゃ何も変わらない」と思う人もいるかもしれません。でも、私はそうは思いません。一人の行動が周りの誰かを変えるかもしれない。そして、その誰かがまた別の誰かに影響を与える。そうやってつながっていけば、きっと社会も世界も少しずつ変わっていくはずです。
私たちの未来は、まだ白紙の状態です。そこにどんな絵を描くのかは、私たち次第です。私は、地球や人、動物が共に生きる優しい未来を描きたい。そのために、小さな一歩を大切に、これからも学び、考え、行動していきたいと思います。だから私はこれからも、身の回りの自然や生き物に目を向け、小さなことでも行動を続けていきたいです。一歩ずつでも前に進めば、未来はきっと変わります。
こどもまんなか育成支援活動講演会
2025/10/03
子どもたちへの体験活動の提供について理解を深め、課題解決に向けて共に考えていくため、多くの子どもたちへの多様な体験機会の提供に関する活動に長年取り組まれてこられた今井悠介(いまい ゆうすけ)さんを講師に、すべての子ども・若者への体験機会の提供に関する講演会を開催しました。
※ YouTubeで公開しています。
動画のURL:https://youtu.be/J_9A7fGkWHE
演題:すべての子ども・若者に体験機会の提供を
講師:今井 悠介 氏
(公益社団法人チャンス・フォー・チルドレン代表理事)
講演後、村岡知事は「体験することによって何か感じるということが成長にとって非常に大きな力になることを改めて感じることができた。体験格差をなくし、子どもたちがやりたいことができる環境をしっかり整えることが大変重要であり、市や町と連携し地域の力を結集して、社会全体で子どもたちの学びや成長を応援していく県づくりをしたい。」と挨拶しました。
※ YouTubeで公開しています。
動画のURL:https://youtu.be/J_9A7fGkWHE
演題:すべての子ども・若者に体験機会の提供を
講師:今井 悠介 氏
(公益社団法人チャンス・フォー・チルドレン代表理事)
講演後、村岡知事は「体験することによって何か感じるということが成長にとって非常に大きな力になることを改めて感じることができた。体験格差をなくし、子どもたちがやりたいことができる環境をしっかり整えることが大変重要であり、市や町と連携し地域の力を結集して、社会全体で子どもたちの学びや成長を応援していく県づくりをしたい。」と挨拶しました。
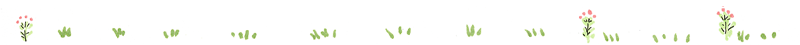
やまぐち子育て連盟 http://yamaguchi-kosodate.net