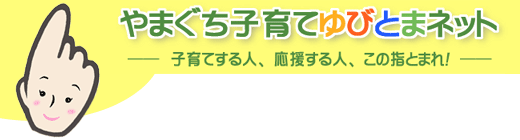|
|
|
令和6年度少年の主張コンクール発表作文紹介(優良賞)
2024/09/26
『自分らしく生きるために』
萩光塩学院中学校 3年 二宮 史織
私は、将来自立して生きるため、学校には行かなくてもいいけれど、勉強はしなければいけないと考えます。学び方は、その人に合った学び方で学ぶといいと思います。学校は死ぬような思いをしてまで行く場所ではありませんが、学校に行くと、質の高い教育が受けられることと同時に、コミュニケーション能力などの社会性を身につけることができます。最近は不登校の児童生徒が増えているというニュースをよく見ます。現在、中学校では約20万人の人が不登校のようです。不登校になる最初のきっかけは体調不良が32.6%と一番多く、最初と別の理由としては勉強がわからないことが41.8%でした。私は小学校5年生の頃からあまり学校に行っていませんでした。そのため、5年生の算数が今でも分からず、基礎が抜けています。このことから学校での学習は大切だと分かりました。
家でも学習する方法として、オンラインで、家でも学校の授業が受けられるようにすることと、子どもの自由を尊重するフリースクール制度を利用することが挙げられます。また、家族からの理解・協力も大切です。家族を含めた誰もが、なぜ学校に行けないんだというような否定的な考えではなく、学校に行けているだけでもすごいという視点を持つことが大事です。受け入れられているということで、自分の心持ちが軽くなります。
アメリカでは、自宅で勉強する「ホームスクール制度」が確立されています。ホームスクール制度は義務教育として認められており、自宅で親や派遣教師から勉強を教わります。つまり、学校以外で学校と同等の教育を受けられるということです。教育を受ける場を選べるアメリカでは、不登校に対する捉え方が日本とは違います。
学校に行き始めた頃、私は遅刻して行き、早退することから始め、少しずつ学校にいる時間を増やしていきました。私は遅刻・早退をするとき、荷物が目立ってみんなに注目されてしまうのが嫌だったので、学校の人と遭遇しないでいける、個別の部屋を用意してもらいたかったです。他にも、クラスの担任ではなく個別の先生がついている、自分が好きなタイミングで帰ることができる、先生が学校に行くことを強制しない、なにもすることのない時間がないこと、メールなど話す以外で先生に意見を伝える方法がある、先生が不登校に理解があり、どう対応すればいいのかわかる、ということがあると安心だと思います。担任の先生がすべて対応してくださっていたので、授業中はやることがなく、課題があっても説明がなくてやり方がわからず、一時間何もすることがないというような時間が多かったです。だから、こんな配慮があればもっと学校に行きやすかったと思います。
社会性を育てるためには、とにかく人と関わることが重要だと考えました。オンライン対話や文通、家族と話すなど身近な人でもいいからとにかく話すことです。自分の意見を分かりやすく伝え、相手の立場を認めながら聞く力が身に付きます。学校では、友達や先生と関わりながら、コミュニケーション能力を身につけることができます。努力する力なども身につきます。学校は苦しい思いをして行くところではないけれど、得られるものがたくさんある場所です。私は将来、自分の経験を生かし、スクールカウンセラーになって、苦しさは取り除いてあげたり、共感してあげたりして、少しでも心のおもりを軽くして、前を向いて生きていけるようにしてあげたいです。
何もしないのはとにかく健康に悪いと思います。だから学校に行かなくても、規則正しい生活習慣を保ち、これから何年も付き合っていく体なので未来の自分の身のために、自分の身を守ることが大切だと考えます。一日三食食べて、運動して、決まった時間に起きて寝ることが勉強よりも大前提として一番大切なことだと思います。
このように学校に行っていなくてもやれることはたくさんあります。学校に行きたくないのなら無理をして行くことはありませんが、自立に向けて、行かないなりに、学ぶことは重要です。自分で自分の未来を選択し、自分らしく生きるために努力を続けることが大切だと考えます。
萩光塩学院中学校 3年 二宮 史織
私は、将来自立して生きるため、学校には行かなくてもいいけれど、勉強はしなければいけないと考えます。学び方は、その人に合った学び方で学ぶといいと思います。学校は死ぬような思いをしてまで行く場所ではありませんが、学校に行くと、質の高い教育が受けられることと同時に、コミュニケーション能力などの社会性を身につけることができます。最近は不登校の児童生徒が増えているというニュースをよく見ます。現在、中学校では約20万人の人が不登校のようです。不登校になる最初のきっかけは体調不良が32.6%と一番多く、最初と別の理由としては勉強がわからないことが41.8%でした。私は小学校5年生の頃からあまり学校に行っていませんでした。そのため、5年生の算数が今でも分からず、基礎が抜けています。このことから学校での学習は大切だと分かりました。
家でも学習する方法として、オンラインで、家でも学校の授業が受けられるようにすることと、子どもの自由を尊重するフリースクール制度を利用することが挙げられます。また、家族からの理解・協力も大切です。家族を含めた誰もが、なぜ学校に行けないんだというような否定的な考えではなく、学校に行けているだけでもすごいという視点を持つことが大事です。受け入れられているということで、自分の心持ちが軽くなります。
アメリカでは、自宅で勉強する「ホームスクール制度」が確立されています。ホームスクール制度は義務教育として認められており、自宅で親や派遣教師から勉強を教わります。つまり、学校以外で学校と同等の教育を受けられるということです。教育を受ける場を選べるアメリカでは、不登校に対する捉え方が日本とは違います。
学校に行き始めた頃、私は遅刻して行き、早退することから始め、少しずつ学校にいる時間を増やしていきました。私は遅刻・早退をするとき、荷物が目立ってみんなに注目されてしまうのが嫌だったので、学校の人と遭遇しないでいける、個別の部屋を用意してもらいたかったです。他にも、クラスの担任ではなく個別の先生がついている、自分が好きなタイミングで帰ることができる、先生が学校に行くことを強制しない、なにもすることのない時間がないこと、メールなど話す以外で先生に意見を伝える方法がある、先生が不登校に理解があり、どう対応すればいいのかわかる、ということがあると安心だと思います。担任の先生がすべて対応してくださっていたので、授業中はやることがなく、課題があっても説明がなくてやり方がわからず、一時間何もすることがないというような時間が多かったです。だから、こんな配慮があればもっと学校に行きやすかったと思います。
社会性を育てるためには、とにかく人と関わることが重要だと考えました。オンライン対話や文通、家族と話すなど身近な人でもいいからとにかく話すことです。自分の意見を分かりやすく伝え、相手の立場を認めながら聞く力が身に付きます。学校では、友達や先生と関わりながら、コミュニケーション能力を身につけることができます。努力する力なども身につきます。学校は苦しい思いをして行くところではないけれど、得られるものがたくさんある場所です。私は将来、自分の経験を生かし、スクールカウンセラーになって、苦しさは取り除いてあげたり、共感してあげたりして、少しでも心のおもりを軽くして、前を向いて生きていけるようにしてあげたいです。
何もしないのはとにかく健康に悪いと思います。だから学校に行かなくても、規則正しい生活習慣を保ち、これから何年も付き合っていく体なので未来の自分の身のために、自分の身を守ることが大切だと考えます。一日三食食べて、運動して、決まった時間に起きて寝ることが勉強よりも大前提として一番大切なことだと思います。
このように学校に行っていなくてもやれることはたくさんあります。学校に行きたくないのなら無理をして行くことはありませんが、自立に向けて、行かないなりに、学ぶことは重要です。自分で自分の未来を選択し、自分らしく生きるために努力を続けることが大切だと考えます。
令和6年度少年の主張コンクール発表作文紹介(優良賞)
2024/09/26
『配慮と差別の境界線』
田布施町立田布施中学校 3年 山本 小春
私はアセクシャル、無性愛と呼ばれるセクシュアリティをもっている。
近年、LGBTQ+の言葉や理解が深まったことにより、私のような珍しいセクシュアリティへの偏見が少なくなっている。そして偏見が少なくなるだけでなく、それを個性として認めてくれるようになった。
だが、最近これらが認められるようになり、ある問題が表に出てきた。それは、配慮と差別の境界線をどうするかという問題だ。
私は以前、好きな人について聞かれたことがあった。その時は、この質問には特別何とも思わなかったのだが、別の友人に「小春は少し考え方が違うから話変えよう」と言われたことがあった。私は、このセリフがどうにも頭から消えなかった。その友人も、私のことを思って話を変えてくれたこともわかっていたのだがどうしても、消えなかった。
そんなとき、「ポリティカルコレクトネス」のやりすぎが問題とされていることを知った。私はこの問題を知ったとき自分と同じようなことで悩んでいる人がいるのだと初めて学んだ。「ポリティカルコレクトネス」「ポリコレ」とは性のことに限られたものではなく人種や年齢、障害の有無などによるマイノリティ・社会的弱者を守るものであるのだが、この「ポリコレ」というものに配慮しすぎており、最近ではその本来の目的が忘れられているように感じる。それは、インターネット上での炎上や映画などの作品群への表現の制限などだ。
本来、人を守るためにある「ポリコレ」をインターネット上での攻撃として使ってもよいのだろうか。そして、「ポリコレ」によって表現を制限してしまっても良いのだろうかと思う。
インターネット上では、「ポリコレ」への配慮ができていないと炎上したり、逆に「ポリコレ」への配慮が難しいということで共感を呼んだり、とても線引きが困難な状態がある。そのため、インターネットというとても広い世界での「ポリコレ」に関するルールや常識を作りそれをたくさんの人で発信することができればそこからインターネット上だけではなく現実でも使えるものになると考える。また、「ポリコレ」についてのルールや常識を作ることで、今よりもよりよい作品製作が行えるのではないだろうか。そして本当の意味での表現の自由がなされると思う。
加えて、私が以前経験したように配慮したつもりであってもそれが別の意味や差別のように感じられることがある。その感じ方は、人によって違いが少なくとも生じてしまうため「ポリコレ」に関するルールや常識はより多くの人と話し合い、多くの変化を繰り返しながら決めていくものだと思う。
だからこそ、たくさんの人が利用しているインターネットを使うことはこの問題にとって有効だ。
このように、差別や偏見が順調に少なくなってきて、私のような珍しいセクシャリティをもつ人が生活しやすくなっている中、配慮と差別の線引きが難しくなってきている。
そのため、私はインターネットを用いて、たくさんの人と話し合い、配慮と差別の違い、そして「ポリコレ」へのルールや常識をつくることによって「LGBTQ+」や「ポリコレ」などの発信をしやすくすると同時に今まで明確に決まったルールがなく手探りであっただろう映画などといった作品群がこれにより本当の意味での表現の自由になるのではないだろうか。
そして、今まで「LGBTQ+」や「ポリコレ」といったものを自分は関係がないと思っていた人にも作品を通して知ってもらうことができるのではないだろうか。
最後に、このように配慮と差別、そして、「ポリコレ」などのルールや常識ができ、どの立場にいる人であっても明るく楽しく過ごすことのできる未来がやって来ることを心から願っている。
田布施町立田布施中学校 3年 山本 小春
私はアセクシャル、無性愛と呼ばれるセクシュアリティをもっている。
近年、LGBTQ+の言葉や理解が深まったことにより、私のような珍しいセクシュアリティへの偏見が少なくなっている。そして偏見が少なくなるだけでなく、それを個性として認めてくれるようになった。
だが、最近これらが認められるようになり、ある問題が表に出てきた。それは、配慮と差別の境界線をどうするかという問題だ。
私は以前、好きな人について聞かれたことがあった。その時は、この質問には特別何とも思わなかったのだが、別の友人に「小春は少し考え方が違うから話変えよう」と言われたことがあった。私は、このセリフがどうにも頭から消えなかった。その友人も、私のことを思って話を変えてくれたこともわかっていたのだがどうしても、消えなかった。
そんなとき、「ポリティカルコレクトネス」のやりすぎが問題とされていることを知った。私はこの問題を知ったとき自分と同じようなことで悩んでいる人がいるのだと初めて学んだ。「ポリティカルコレクトネス」「ポリコレ」とは性のことに限られたものではなく人種や年齢、障害の有無などによるマイノリティ・社会的弱者を守るものであるのだが、この「ポリコレ」というものに配慮しすぎており、最近ではその本来の目的が忘れられているように感じる。それは、インターネット上での炎上や映画などの作品群への表現の制限などだ。
本来、人を守るためにある「ポリコレ」をインターネット上での攻撃として使ってもよいのだろうか。そして、「ポリコレ」によって表現を制限してしまっても良いのだろうかと思う。
インターネット上では、「ポリコレ」への配慮ができていないと炎上したり、逆に「ポリコレ」への配慮が難しいということで共感を呼んだり、とても線引きが困難な状態がある。そのため、インターネットというとても広い世界での「ポリコレ」に関するルールや常識を作りそれをたくさんの人で発信することができればそこからインターネット上だけではなく現実でも使えるものになると考える。また、「ポリコレ」についてのルールや常識を作ることで、今よりもよりよい作品製作が行えるのではないだろうか。そして本当の意味での表現の自由がなされると思う。
加えて、私が以前経験したように配慮したつもりであってもそれが別の意味や差別のように感じられることがある。その感じ方は、人によって違いが少なくとも生じてしまうため「ポリコレ」に関するルールや常識はより多くの人と話し合い、多くの変化を繰り返しながら決めていくものだと思う。
だからこそ、たくさんの人が利用しているインターネットを使うことはこの問題にとって有効だ。
このように、差別や偏見が順調に少なくなってきて、私のような珍しいセクシャリティをもつ人が生活しやすくなっている中、配慮と差別の線引きが難しくなってきている。
そのため、私はインターネットを用いて、たくさんの人と話し合い、配慮と差別の違い、そして「ポリコレ」へのルールや常識をつくることによって「LGBTQ+」や「ポリコレ」などの発信をしやすくすると同時に今まで明確に決まったルールがなく手探りであっただろう映画などといった作品群がこれにより本当の意味での表現の自由になるのではないだろうか。
そして、今まで「LGBTQ+」や「ポリコレ」といったものを自分は関係がないと思っていた人にも作品を通して知ってもらうことができるのではないだろうか。
最後に、このように配慮と差別、そして、「ポリコレ」などのルールや常識ができ、どの立場にいる人であっても明るく楽しく過ごすことのできる未来がやって来ることを心から願っている。
令和6年度少年の主張コンクール発表作文紹介(優良賞)
2024/09/26
『本当の友達関係とは』
周南市立太華中学校 3年 水沼 花梨
教室で響く笑い声。それは、いつも、みんなにとって「楽しい」と感じられるものでしょうか。私は、時々、一緒に笑えない自分に気づくことがあります。例えば、授業で誰かが答えを間違えたとき、冷たい笑いを感じます。「なんでこんな問題も解けないわけ?」というセリフが聞こえてきそうな笑い。皆さんは、この「笑い」について、どう思いますか。
小学校2年生の頃、算数の時間に、答えを間違えたことがあります。周りから聞こえる笑いが、自分を蔑むように聞こえ、その後、自分から手を挙げることができなくなりました。
桜が舞う季節が何回か過ぎたある日、クラスメイトが容姿を批判されているところにでくわしました。「あなたもそう思うよね」と声を掛けられ、「そうだね」と思わず言ってしまいました。いろいろな経験を重ねて、今では、同調圧力を掛けられても人に流されない自分の芯ができました。しかし、それと同時に、「自分もそう思われているのではないか」という不安に駆られるようになってしまいました。他の人の話題を耳にしても、自分のことを言われているように辛くなったり、自分が笑われているのではないかと聞き耳を立てたりしてしまう自分自身が嫌になります。友達と仲良くしていても、「自分は友達を演じているのではないか。本当の友達ではないのではないか」と自分自身を疑ったりしてしまうのです。
ふとしたきっかけで、こんなふうになってしまうのは、きっと、私だけではないでしょう。もしかすると、もっと深刻に捉えて、自分を傷つける人もいるかもしれません。
人は、なぜ、自分より下の人を見つけることによって安心したり、自分という存在を認めてもらえない悔しさを他人にぶつけたりするのでしょうか。それは、人の弱さの表れだと私は思います。いじめも、差別も、迫害も根っこは同じ。そう考えると、これらは本当に根が深く、どうしようもないことなのかもしれないとすら思えてきます。そして、そのきっかけになるのは「小さな違い」だったりするのです。さらに、自分が矢面に立ちたくないために、本心とは違う反応をしてしまうことも多く、これも人の弱さの表れだと思います。「目立たないこと」「同じであること」は、そんなに大切なことなのでしょうか。
「多様性」という言葉を、よく耳にします。話し合いの場面でも、いろいろな意見が出る方が、気づきや発見があって盛り上がります。まして、異なる経験をもつ人たちが集まる集団でどんどんアイディアを出すことができたらどんなに楽しいでしょうか。
私は吹奏楽部に所属していますが、本当にさまざまなキャラクターの人がいます。そして、それぞれの奏でる音は、それこそ多種多様です。そして、それが一つに合わさった時の重厚感に、いつも感動することができます。
それぞれの人がもっている個性や視点を、「ずれている」とか「性格悪いよね」と、ネガティブな言葉ですぐに「はじく」のではなく、いろんな考え方を受け入れ、交流することで、私たちを取り巻く世界は「音楽」みたいに豊かになっていくのではないか。最近、私はそのように思います。
周囲の反応を気にせず発言でき、心から「楽しい」と感じながら笑い合えるクラスになるといいなあ。そのためには、どうするべきでしょうか。
「隗より始めよ。」私にできることを考えてみました。まずは疑心暗鬼をやめて、明るく笑うこと。さらに、友達の発言に「いいね!」と反応すること。ちょっとくらい間違えてしまっても「大丈夫!」と思い、笑いとばせるような友達関係を築きたいです。私から明るく、楽しい波が広がっていきますように!
周南市立太華中学校 3年 水沼 花梨
教室で響く笑い声。それは、いつも、みんなにとって「楽しい」と感じられるものでしょうか。私は、時々、一緒に笑えない自分に気づくことがあります。例えば、授業で誰かが答えを間違えたとき、冷たい笑いを感じます。「なんでこんな問題も解けないわけ?」というセリフが聞こえてきそうな笑い。皆さんは、この「笑い」について、どう思いますか。
小学校2年生の頃、算数の時間に、答えを間違えたことがあります。周りから聞こえる笑いが、自分を蔑むように聞こえ、その後、自分から手を挙げることができなくなりました。
桜が舞う季節が何回か過ぎたある日、クラスメイトが容姿を批判されているところにでくわしました。「あなたもそう思うよね」と声を掛けられ、「そうだね」と思わず言ってしまいました。いろいろな経験を重ねて、今では、同調圧力を掛けられても人に流されない自分の芯ができました。しかし、それと同時に、「自分もそう思われているのではないか」という不安に駆られるようになってしまいました。他の人の話題を耳にしても、自分のことを言われているように辛くなったり、自分が笑われているのではないかと聞き耳を立てたりしてしまう自分自身が嫌になります。友達と仲良くしていても、「自分は友達を演じているのではないか。本当の友達ではないのではないか」と自分自身を疑ったりしてしまうのです。
ふとしたきっかけで、こんなふうになってしまうのは、きっと、私だけではないでしょう。もしかすると、もっと深刻に捉えて、自分を傷つける人もいるかもしれません。
人は、なぜ、自分より下の人を見つけることによって安心したり、自分という存在を認めてもらえない悔しさを他人にぶつけたりするのでしょうか。それは、人の弱さの表れだと私は思います。いじめも、差別も、迫害も根っこは同じ。そう考えると、これらは本当に根が深く、どうしようもないことなのかもしれないとすら思えてきます。そして、そのきっかけになるのは「小さな違い」だったりするのです。さらに、自分が矢面に立ちたくないために、本心とは違う反応をしてしまうことも多く、これも人の弱さの表れだと思います。「目立たないこと」「同じであること」は、そんなに大切なことなのでしょうか。
「多様性」という言葉を、よく耳にします。話し合いの場面でも、いろいろな意見が出る方が、気づきや発見があって盛り上がります。まして、異なる経験をもつ人たちが集まる集団でどんどんアイディアを出すことができたらどんなに楽しいでしょうか。
私は吹奏楽部に所属していますが、本当にさまざまなキャラクターの人がいます。そして、それぞれの奏でる音は、それこそ多種多様です。そして、それが一つに合わさった時の重厚感に、いつも感動することができます。
それぞれの人がもっている個性や視点を、「ずれている」とか「性格悪いよね」と、ネガティブな言葉ですぐに「はじく」のではなく、いろんな考え方を受け入れ、交流することで、私たちを取り巻く世界は「音楽」みたいに豊かになっていくのではないか。最近、私はそのように思います。
周囲の反応を気にせず発言でき、心から「楽しい」と感じながら笑い合えるクラスになるといいなあ。そのためには、どうするべきでしょうか。
「隗より始めよ。」私にできることを考えてみました。まずは疑心暗鬼をやめて、明るく笑うこと。さらに、友達の発言に「いいね!」と反応すること。ちょっとくらい間違えてしまっても「大丈夫!」と思い、笑いとばせるような友達関係を築きたいです。私から明るく、楽しい波が広がっていきますように!
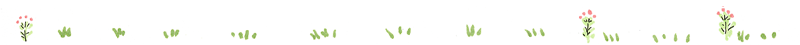
やまぐち子育て連盟 http://yamaguchi-kosodate.net