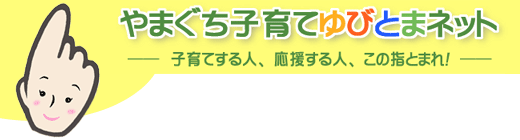|
|
|
令和6年度少年の主張コンクール発表作文紹介 優秀(県民会議会長賞)
2024/09/26
『言葉が伝えた心の支え』
周南市立富田中学校 2年 田邊 優衣
あなたが「心の支え」と聞いて最初に思い浮かべるのは何ですか。自分の心の支えのことですか、誰かの心の支えのことですか、それ以外のことですか。人によって心にぴったりと当てはまるものは違いますが、私が最初に思い浮かぶのは私自身の心の支えである、親友です。
「全部、受け入れるよ。」
これは彼女が放った言葉の中で一番印象に残り、一番嬉しかった言葉です。
私と親友の出会いは、小学4年生のとき、彼女が転校生として同じクラスに転入したことでした。このときから親友の歯車が動き始めました。気づいたら仲良くなって、気づいたら親友と呼び合って、気づいたら心の支えとなっていました。そんな「気づいたら」の連発が友情を深めていきました。
私たちはみんなをまとめたり、リーダーに選ばれたりすることが多く、そのような部分でも協力することが多かったです。中学生になってからも同じ部活動に所属し、ずっと変わらない関係です。同級生だけではなく、先生方、両親も公認の仲良しコンビです。
ここまで聞くと何事も順調に進んでいるように感じられると思います。ですが、立ち止まっていることばかりです。
「止まれ」のサインを出しているのは私の吃音症です。吃音症とは言葉を繰り返したり、伸ばしたり、出づらくなってしまう症状が現れることをいいます。治療法は確立されていません。私の場合、あ行が言いにくくなることが多く、挨拶ができなかったり、話すときに最初の一音が出なかったりします。また、親友の名前もあ行から始まり、親友の名前でさえ言えないこともあります。すごく素敵な名前なのに…。名前を呼べないことはかなり辛いことです。明るい話だったのに、私のせいで気を使わせてしまうこと、話したいことが伝えられないこと。本当に嫌でした。
吃音をもつ人は日本では約120万人100人に1人が吃音により少しでも苦に感じたことがあるということです。また、言葉の出やすさには波があります。言葉が出にくいときは「どうやったら読みやすいか」を工夫しています。しかし、原稿を睨みつけながら音が出ずに息だけが吐き出されます。声になるはずの音と文字が分裂して喉に張りつく感覚があります。「吃音だから」といって諦めてきたことが今までたくさんありました。
ですが、今は音と文字が分裂しようとも、張りつこうともやりたいと思ったことに挑戦するように心がけています。なぜなら「全てを受け入れる」と言ってくれる親友がいるからです。言えなくても、後でめいいっぱい話を聞いてもらおう。上手くいってもたくさん話そう。こう思えているからです。本人に聞いてみると、言葉が詰まったときは「ゆっくりでいいよ」と「頑張れ」と思ってくれているそうです。「やっぱり」と思いました。やっぱり私の親友は受け入れてくれている。受け入れてくれているからこう思えるのだ、と。だから、親友とは楽に話すことができています。立ち止まりながら、それを糧として私たちは少しずつ前に進んでいるのです。
私が伝えたいことは、「心の支え」は自分らしさを与えてくれるもの、一緒に歩んでくれるものだということです。私は吃音を通して気づくことができましたが、きっと、吃音がなくても同じことを思っているはずです。出会えたから、私は気づくことができ、挑戦もできています。彼女も違う形で同じように思ってくれているそうなので、「お互いが心の支え」なのです。「支え」があるからこそ、「自立」が輝くと思っています。
あなたが「心の支え」と聞いて最初に思い浮かべるのは何ですか。
周南市立富田中学校 2年 田邊 優衣
あなたが「心の支え」と聞いて最初に思い浮かべるのは何ですか。自分の心の支えのことですか、誰かの心の支えのことですか、それ以外のことですか。人によって心にぴったりと当てはまるものは違いますが、私が最初に思い浮かぶのは私自身の心の支えである、親友です。
「全部、受け入れるよ。」
これは彼女が放った言葉の中で一番印象に残り、一番嬉しかった言葉です。
私と親友の出会いは、小学4年生のとき、彼女が転校生として同じクラスに転入したことでした。このときから親友の歯車が動き始めました。気づいたら仲良くなって、気づいたら親友と呼び合って、気づいたら心の支えとなっていました。そんな「気づいたら」の連発が友情を深めていきました。
私たちはみんなをまとめたり、リーダーに選ばれたりすることが多く、そのような部分でも協力することが多かったです。中学生になってからも同じ部活動に所属し、ずっと変わらない関係です。同級生だけではなく、先生方、両親も公認の仲良しコンビです。
ここまで聞くと何事も順調に進んでいるように感じられると思います。ですが、立ち止まっていることばかりです。
「止まれ」のサインを出しているのは私の吃音症です。吃音症とは言葉を繰り返したり、伸ばしたり、出づらくなってしまう症状が現れることをいいます。治療法は確立されていません。私の場合、あ行が言いにくくなることが多く、挨拶ができなかったり、話すときに最初の一音が出なかったりします。また、親友の名前もあ行から始まり、親友の名前でさえ言えないこともあります。すごく素敵な名前なのに…。名前を呼べないことはかなり辛いことです。明るい話だったのに、私のせいで気を使わせてしまうこと、話したいことが伝えられないこと。本当に嫌でした。
吃音をもつ人は日本では約120万人100人に1人が吃音により少しでも苦に感じたことがあるということです。また、言葉の出やすさには波があります。言葉が出にくいときは「どうやったら読みやすいか」を工夫しています。しかし、原稿を睨みつけながら音が出ずに息だけが吐き出されます。声になるはずの音と文字が分裂して喉に張りつく感覚があります。「吃音だから」といって諦めてきたことが今までたくさんありました。
ですが、今は音と文字が分裂しようとも、張りつこうともやりたいと思ったことに挑戦するように心がけています。なぜなら「全てを受け入れる」と言ってくれる親友がいるからです。言えなくても、後でめいいっぱい話を聞いてもらおう。上手くいってもたくさん話そう。こう思えているからです。本人に聞いてみると、言葉が詰まったときは「ゆっくりでいいよ」と「頑張れ」と思ってくれているそうです。「やっぱり」と思いました。やっぱり私の親友は受け入れてくれている。受け入れてくれているからこう思えるのだ、と。だから、親友とは楽に話すことができています。立ち止まりながら、それを糧として私たちは少しずつ前に進んでいるのです。
私が伝えたいことは、「心の支え」は自分らしさを与えてくれるもの、一緒に歩んでくれるものだということです。私は吃音を通して気づくことができましたが、きっと、吃音がなくても同じことを思っているはずです。出会えたから、私は気づくことができ、挑戦もできています。彼女も違う形で同じように思ってくれているそうなので、「お互いが心の支え」なのです。「支え」があるからこそ、「自立」が輝くと思っています。
あなたが「心の支え」と聞いて最初に思い浮かべるのは何ですか。
令和6年度少年の主張コンクール発表作文紹介 優秀(県民会議会長賞)
2024/09/26
『平等から公平へ』
周南市立富田中学校 2年 藤井 香蓮
2022年4月に入学した私の中学校は、この年から学ランやセーラー服からブレザー型の制服に移行しました。移行理由は、制服のもつ機能性・安全性や今後の社会変化に対応できるためといいます。ブレザーは左右どちらにも取り付けが可能なボタン仕様で、ボトムスにはスラックスとスカートが用意され、自由に選ぶことができます。私はスラックスだとトイレが難しいと考えてスカートを選びましたが、偶然被服店で会った友達はスラックスにすると言っていました。
さて、ここまで私の話を聞いた方の中には、私の性別が男なのか女なのか文脈から読み取ろうとした方もいるのではないでしょうか。「スカートを選んだ」とあるので、女の子なんだろうなと直感的に思った方もいるでしょう。答えはイエスです。私は生物学上も性自認も女であり、性的指向は男です。
入学当初感じたことは、生物学上「女」とされる人の制服姿は自由度が高い反面、生物学上「男」とされる人の制服姿はスラックス一択と、選択に差があることでした。
現在、私は中学2年生に進級し、楽しい学校生活を送っています。たくさんの人と関わる中で、入学した頃よりも一人一人を深く知る機会が増えたように思います。中には、生物学上「女」でも性自認が異なる人、性的指向が女の人、どちらも好きになるという、性的指向が男と女両方という人もいます。私の周りにも生物学上「女」とされる人の中に、様々な性的マイノリティーの友達がいるかもしれません。だとすれば、生物学上「男」とされる人の中にも、様々な性的マイノリティーの友達がいると考えるのは不思議なことではありません。学ランかブレザーにスラックス姿で日々学校生活をやり過ごす性自認が女である友達がいるかもしれません。制服、着替え、トイレといった日常生活を苦痛に感じていても、それを声に出せない友達がいるかもしれません。
社会に出る前の私たち10代やそれより下の年齢の者は、園や学校という場所が公的社会の全てで、小さくてもそれが私たちの社会なのです。性という観点から今いる社会に生きづらさを感じているとしたら、そこから先の未来に希望を見出せないのではないでしょうか。きっと昔から様々な性的マイノリティーは存在していたはずで、それが情報社会が加速する近年、私たちの身近な存在になり、だんだんと定着しつつあるのでしょう。中学校においても、社会変化に対応できるよう制服が移行しました。そのような時代の移り変わりの「はざま」で私たちは生きているのだと思います。
以前、学校の道徳の授業で公平とは何かを考える機会がありました。私はすぐに平等という言葉が思い浮かびましたが、平等と公平とは似ているようで全く別の意味であることを知りました。平等とは誰もが皆等しいこと、全員に対して同じ対応をすることで、公平とは能力や状況に応じて適切な扱いを受けること、全員が同じ機会を確保できるようにすることです。平等と公平について様々な性の観点から考えると、制服移行は性別を区別せず生徒一人一人に平等なものが提供された通過点に過ぎません。そして、多様な性を生きる私たちが学校という社会の中で、自分は受け入れられていると実感できることが真の公平といえるでしょう。しかし、平等から公平を築くことは容易ではありません。相手には見えていることも自分には見えていないことがあるはずです。様々な問題に気づけること、どんな小さい事でも自分事として捉える意識を私たち一人一人が持つことが大切なのではないでしょうか。平等から公平な学校社会の実現は、そこから羽ばたく私たちの未来につながる希望の力になると私は信じています。
周南市立富田中学校 2年 藤井 香蓮
2022年4月に入学した私の中学校は、この年から学ランやセーラー服からブレザー型の制服に移行しました。移行理由は、制服のもつ機能性・安全性や今後の社会変化に対応できるためといいます。ブレザーは左右どちらにも取り付けが可能なボタン仕様で、ボトムスにはスラックスとスカートが用意され、自由に選ぶことができます。私はスラックスだとトイレが難しいと考えてスカートを選びましたが、偶然被服店で会った友達はスラックスにすると言っていました。
さて、ここまで私の話を聞いた方の中には、私の性別が男なのか女なのか文脈から読み取ろうとした方もいるのではないでしょうか。「スカートを選んだ」とあるので、女の子なんだろうなと直感的に思った方もいるでしょう。答えはイエスです。私は生物学上も性自認も女であり、性的指向は男です。
入学当初感じたことは、生物学上「女」とされる人の制服姿は自由度が高い反面、生物学上「男」とされる人の制服姿はスラックス一択と、選択に差があることでした。
現在、私は中学2年生に進級し、楽しい学校生活を送っています。たくさんの人と関わる中で、入学した頃よりも一人一人を深く知る機会が増えたように思います。中には、生物学上「女」でも性自認が異なる人、性的指向が女の人、どちらも好きになるという、性的指向が男と女両方という人もいます。私の周りにも生物学上「女」とされる人の中に、様々な性的マイノリティーの友達がいるかもしれません。だとすれば、生物学上「男」とされる人の中にも、様々な性的マイノリティーの友達がいると考えるのは不思議なことではありません。学ランかブレザーにスラックス姿で日々学校生活をやり過ごす性自認が女である友達がいるかもしれません。制服、着替え、トイレといった日常生活を苦痛に感じていても、それを声に出せない友達がいるかもしれません。
社会に出る前の私たち10代やそれより下の年齢の者は、園や学校という場所が公的社会の全てで、小さくてもそれが私たちの社会なのです。性という観点から今いる社会に生きづらさを感じているとしたら、そこから先の未来に希望を見出せないのではないでしょうか。きっと昔から様々な性的マイノリティーは存在していたはずで、それが情報社会が加速する近年、私たちの身近な存在になり、だんだんと定着しつつあるのでしょう。中学校においても、社会変化に対応できるよう制服が移行しました。そのような時代の移り変わりの「はざま」で私たちは生きているのだと思います。
以前、学校の道徳の授業で公平とは何かを考える機会がありました。私はすぐに平等という言葉が思い浮かびましたが、平等と公平とは似ているようで全く別の意味であることを知りました。平等とは誰もが皆等しいこと、全員に対して同じ対応をすることで、公平とは能力や状況に応じて適切な扱いを受けること、全員が同じ機会を確保できるようにすることです。平等と公平について様々な性の観点から考えると、制服移行は性別を区別せず生徒一人一人に平等なものが提供された通過点に過ぎません。そして、多様な性を生きる私たちが学校という社会の中で、自分は受け入れられていると実感できることが真の公平といえるでしょう。しかし、平等から公平を築くことは容易ではありません。相手には見えていることも自分には見えていないことがあるはずです。様々な問題に気づけること、どんな小さい事でも自分事として捉える意識を私たち一人一人が持つことが大切なのではないでしょうか。平等から公平な学校社会の実現は、そこから羽ばたく私たちの未来につながる希望の力になると私は信じています。
令和6年度少年の主張コンクール発表作文紹介 優秀(教育長賞)
2024/09/26
『そうじゃないかも』
萩市立萩東中学校 2年 松岡 礼文
「えっ、野球部じゃないの?」
初対面の人が僕にこの言葉をかける確率はかなり高い。僕と同世代の人から高齢の方まで、どの年代の人も、僕を一目見て野球部員だと思うらしい。僕の丸刈りのヘアスタイルは、ごく当たり前に野球少年に変換される。野球部員に間違えられても、「またか」と思う程度で、むしろ会話の糸口をつかむことができて助かるくらいの気分だ。
「こんな髪型ですけど、吹奏楽部員です。」
と、自分から言うことさえあった。そんなふうに笑って会話をしながらも、どこか違和感があった。
「丸刈りは野球少年」という多くの人が共有している認識は、ここに僕がいる以上、正しくはない。にもかかわらず、よどみない会話をしたいがために、その固定的な見方を利用しているのが、まぎれもなくこの僕だ。正しくないことを知っているのに、正すこともなく、茶化しているようで、あらためて考えると恥ずかしい。
野球少年に間違えられることでは気分を害することはないが、固定的な見方によって、悲しい思いをしたり、傷ついたり、悔しさを感じることはある。例えば、
「男子なんだから泣くな。」
と言われると、ますます泣きたくなるように。そのようなものの見方から、差別や争いごとが生じていることも、これまで見聞きしてきた。一方的な決めつけや偏見が他者や自分の可能性を奪うことがある。そういう社会を生きるのは、正直いやだ。
目に見えるものを、そのまま単純にそれとして受け取ることは難しい。丸刈りを見れば、野球少年が思い浮かび、スカートを見れば女性を連想するように、目に見えるものとは別の意味を伴って、認識してしまう。僕は一体いつ、丸刈りと野球少年を結びつける見方を身につけたのだろう。思い出そうとしても無理だ。いつの間にか、なんとなく手にしていた。
固定的なものの見方がたくさんの人に共有されると、特定の社会では、それが「ふつう」や「当たり前」になり、あたかも判断基準のような働きをする。しかし、その基準はもっともらしいけれど、必ずしも正しいわけではない。それは、暮らしている国や地域の歴史、文化、習慣によって異なる。性別や年齢による違いもあるだろう。つまり、それは絶対的なものではないし、不変的なものでもない。目に見えるものがすべてではないことも知ってはいるが、自分の中に根付く「ふつう」に寄りかかってしまうのも事実だ。積極的に取り込もうとしたつもりはないのに、無自覚に持っている固定的な見方。それを僕から無くすことは難しいのかもしれない。
それならば、固定的な見方を持つ自分を認めつつ、その見方が不確かなものだという自覚を持つしかない。無意識に自分に根づく価値観をゼロにすることはできなくても、その価値観に対して「そうじゃないかも」という声を自分にかける努力なら、僕にも続けることができる。
自分が見ているものよりも、見えていないものの方が圧倒的に多い。僕に見えていないものも、誰かの目には映っているだろう。他者を思いやること、尊重すること、多様であることを認めることとは、僕には見えていない景色を、他の人は見つめているのだと感じることなのではないかと思う。固定的な見方で不用意に他者を傷つけたり、その見方を捨てきれない自分に嫌気がさしたりするばかりの毎日はごめんだ。だから、僕は自分のものの見方、感じ方に、「そうじゃないかも」と、いつも問い続けられるような人でありたい。他者や世界とのつながりが、もっと和やかで温かいものになるように。
萩市立萩東中学校 2年 松岡 礼文
「えっ、野球部じゃないの?」
初対面の人が僕にこの言葉をかける確率はかなり高い。僕と同世代の人から高齢の方まで、どの年代の人も、僕を一目見て野球部員だと思うらしい。僕の丸刈りのヘアスタイルは、ごく当たり前に野球少年に変換される。野球部員に間違えられても、「またか」と思う程度で、むしろ会話の糸口をつかむことができて助かるくらいの気分だ。
「こんな髪型ですけど、吹奏楽部員です。」
と、自分から言うことさえあった。そんなふうに笑って会話をしながらも、どこか違和感があった。
「丸刈りは野球少年」という多くの人が共有している認識は、ここに僕がいる以上、正しくはない。にもかかわらず、よどみない会話をしたいがために、その固定的な見方を利用しているのが、まぎれもなくこの僕だ。正しくないことを知っているのに、正すこともなく、茶化しているようで、あらためて考えると恥ずかしい。
野球少年に間違えられることでは気分を害することはないが、固定的な見方によって、悲しい思いをしたり、傷ついたり、悔しさを感じることはある。例えば、
「男子なんだから泣くな。」
と言われると、ますます泣きたくなるように。そのようなものの見方から、差別や争いごとが生じていることも、これまで見聞きしてきた。一方的な決めつけや偏見が他者や自分の可能性を奪うことがある。そういう社会を生きるのは、正直いやだ。
目に見えるものを、そのまま単純にそれとして受け取ることは難しい。丸刈りを見れば、野球少年が思い浮かび、スカートを見れば女性を連想するように、目に見えるものとは別の意味を伴って、認識してしまう。僕は一体いつ、丸刈りと野球少年を結びつける見方を身につけたのだろう。思い出そうとしても無理だ。いつの間にか、なんとなく手にしていた。
固定的なものの見方がたくさんの人に共有されると、特定の社会では、それが「ふつう」や「当たり前」になり、あたかも判断基準のような働きをする。しかし、その基準はもっともらしいけれど、必ずしも正しいわけではない。それは、暮らしている国や地域の歴史、文化、習慣によって異なる。性別や年齢による違いもあるだろう。つまり、それは絶対的なものではないし、不変的なものでもない。目に見えるものがすべてではないことも知ってはいるが、自分の中に根付く「ふつう」に寄りかかってしまうのも事実だ。積極的に取り込もうとしたつもりはないのに、無自覚に持っている固定的な見方。それを僕から無くすことは難しいのかもしれない。
それならば、固定的な見方を持つ自分を認めつつ、その見方が不確かなものだという自覚を持つしかない。無意識に自分に根づく価値観をゼロにすることはできなくても、その価値観に対して「そうじゃないかも」という声を自分にかける努力なら、僕にも続けることができる。
自分が見ているものよりも、見えていないものの方が圧倒的に多い。僕に見えていないものも、誰かの目には映っているだろう。他者を思いやること、尊重すること、多様であることを認めることとは、僕には見えていない景色を、他の人は見つめているのだと感じることなのではないかと思う。固定的な見方で不用意に他者を傷つけたり、その見方を捨てきれない自分に嫌気がさしたりするばかりの毎日はごめんだ。だから、僕は自分のものの見方、感じ方に、「そうじゃないかも」と、いつも問い続けられるような人でありたい。他者や世界とのつながりが、もっと和やかで温かいものになるように。
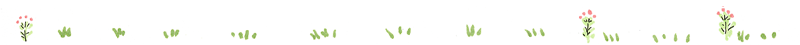
やまぐち子育て連盟 http://yamaguchi-kosodate.net