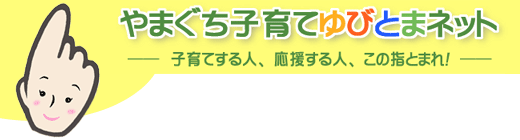|
|
|
令和7年度少年の主張コンクール発表作文紹介(優良賞)
2025/10/03
「この一瞬にすべてを込めて」
下松市立久保中学校 3年 岡村 美咲
私たちの人生は、数え切れないほどの一瞬の積み重ねでできている。一年、一か月、一日、一時間、一分、一秒。どれも貴重な時間だ。私たちは往々にして未来ばかり考え、過去に囚われ、肝心の「今」を見失うことがある。私もそうだった。
中学二年生の冬。その日はいつも通り、大好きなハンドボールを、大好きな仲間たちとプレーしていた。その日行われるのは三試合。第一試合から、予想もしなかった未来が待っていたのだ。前半、戦闘を繰り広げている中で相手選手と衝突し、後頭部を強打した。痛かったのかもしれないが、私は、試合のことだけを考え、そのままプレーを続けた。大丈夫だろう、そんな軽い気持ちで残り二試合も終え、帰路に着いた。その日は、珍しく帰りの車の中からどっと疲れが出て、帰宅後、すぐに休んだ。翌日から、頭痛が続いた。病院では、脳振盪と診断された。「休んでいればすぐ治る。」私は、自分にそう言い聞かせた。
しかし、数週間後に私の生活はガラッと変わった。いつも通りに学校生活を送るのが辛いのだ。クラスメイトの声、机や椅子などの物音、全てが普段の五倍くらいの音量で耳に入ってくる。さらには、照明や太陽光などの明るい空間にいることも辛かった。
次の受診で迫られたのは、二週間の点滴入院か自宅療養の二択。「家がいい。」私はそう言った。自宅療養中は、毎日2ℓのスポーツドリンク摂取、食事やトイレ、風呂以外は横になる。これが、私に与えられた、体を治すためのものだ。今まで普通に過ごしてきた日常ががらりと変わった。分かってはいても、何もできない日々の苦しさ・辛さは、今でも鮮明に思い出すことができる。
それを変えてくれたのは、一人の同級生。一緒にたくさんの水分をとってくれた。学校もあるのに、たくさんの言葉をくれた。おかげで、私の苦しさは楽しさに変わっていった。
三年生。私は自宅療養から解放され、毎日楽しい日々を送っている。幸せだ。勉強できること、友達と他愛のない話をすること、そして、何より、こうして学校に通えることが。それまでの私は、友達と話をすることは当たり前だと思っていた。勉強するのが面倒くさいなと思ったこともある。大好きなハンドボールだってそう。きつい練習の時、思い通りのプレーができず先生に怒られたときは、嫌だなと思った。でも、今まで何気なく行っていた、当たり前と思っていたことが、実は当たり前ではなく、有難いことなのだと気付いた。
ハンドボールができなかった期間は、本当に辛かった。再びコートに立てるようになったのは三年五月。それまでは、チームメイトのために準備や声出し等、できることを頑張った。その中で、試合にでるのは当たり前じゃない、たくさんの人に支えられているからこそプレーできるのだと実感した。また、コートに立てない人の辛さも分かった。試合に出たいという思いは、誰だってある。だから、コートに立てて当然ではなく、コートに立てて有難いという気持ちをもってプレーしたいと強く思うようになった。久しぶりにチームメイトと練習をした日の感動は、これからも忘れることはないだろう。そして、今まで以上にハンドボールが好きになった。
人生は何が起こるか分からない。私は、この経験以来、「今」を意識するようになった。一流のアスリートやアーティストは、限界を超えた最高のパフォーマンスをするために、練習や準備の段階から、「今」に全神経を集中させている。私はアスリートではないが、後悔しないように「今」を精一杯生きていきたい。そして、その「今」を「明日」という未来に繋げていきたい。だって、今の私は、過去の私が作ってくれたものだから。
下松市立久保中学校 3年 岡村 美咲
私たちの人生は、数え切れないほどの一瞬の積み重ねでできている。一年、一か月、一日、一時間、一分、一秒。どれも貴重な時間だ。私たちは往々にして未来ばかり考え、過去に囚われ、肝心の「今」を見失うことがある。私もそうだった。
中学二年生の冬。その日はいつも通り、大好きなハンドボールを、大好きな仲間たちとプレーしていた。その日行われるのは三試合。第一試合から、予想もしなかった未来が待っていたのだ。前半、戦闘を繰り広げている中で相手選手と衝突し、後頭部を強打した。痛かったのかもしれないが、私は、試合のことだけを考え、そのままプレーを続けた。大丈夫だろう、そんな軽い気持ちで残り二試合も終え、帰路に着いた。その日は、珍しく帰りの車の中からどっと疲れが出て、帰宅後、すぐに休んだ。翌日から、頭痛が続いた。病院では、脳振盪と診断された。「休んでいればすぐ治る。」私は、自分にそう言い聞かせた。
しかし、数週間後に私の生活はガラッと変わった。いつも通りに学校生活を送るのが辛いのだ。クラスメイトの声、机や椅子などの物音、全てが普段の五倍くらいの音量で耳に入ってくる。さらには、照明や太陽光などの明るい空間にいることも辛かった。
次の受診で迫られたのは、二週間の点滴入院か自宅療養の二択。「家がいい。」私はそう言った。自宅療養中は、毎日2ℓのスポーツドリンク摂取、食事やトイレ、風呂以外は横になる。これが、私に与えられた、体を治すためのものだ。今まで普通に過ごしてきた日常ががらりと変わった。分かってはいても、何もできない日々の苦しさ・辛さは、今でも鮮明に思い出すことができる。
それを変えてくれたのは、一人の同級生。一緒にたくさんの水分をとってくれた。学校もあるのに、たくさんの言葉をくれた。おかげで、私の苦しさは楽しさに変わっていった。
三年生。私は自宅療養から解放され、毎日楽しい日々を送っている。幸せだ。勉強できること、友達と他愛のない話をすること、そして、何より、こうして学校に通えることが。それまでの私は、友達と話をすることは当たり前だと思っていた。勉強するのが面倒くさいなと思ったこともある。大好きなハンドボールだってそう。きつい練習の時、思い通りのプレーができず先生に怒られたときは、嫌だなと思った。でも、今まで何気なく行っていた、当たり前と思っていたことが、実は当たり前ではなく、有難いことなのだと気付いた。
ハンドボールができなかった期間は、本当に辛かった。再びコートに立てるようになったのは三年五月。それまでは、チームメイトのために準備や声出し等、できることを頑張った。その中で、試合にでるのは当たり前じゃない、たくさんの人に支えられているからこそプレーできるのだと実感した。また、コートに立てない人の辛さも分かった。試合に出たいという思いは、誰だってある。だから、コートに立てて当然ではなく、コートに立てて有難いという気持ちをもってプレーしたいと強く思うようになった。久しぶりにチームメイトと練習をした日の感動は、これからも忘れることはないだろう。そして、今まで以上にハンドボールが好きになった。
人生は何が起こるか分からない。私は、この経験以来、「今」を意識するようになった。一流のアスリートやアーティストは、限界を超えた最高のパフォーマンスをするために、練習や準備の段階から、「今」に全神経を集中させている。私はアスリートではないが、後悔しないように「今」を精一杯生きていきたい。そして、その「今」を「明日」という未来に繋げていきたい。だって、今の私は、過去の私が作ってくれたものだから。
令和7年度少年の主張コンクール発表作文紹介 最優秀(県知事賞)
2025/10/03
「「食」と向き合う」
山口県立高森みどり中学校 3年 須田 青慈
人は、生まれて間もない頃の記憶をもっていない。しかし、そんな時期に、僕には人生を変えるような出来事があった。千葉県松戸市で過ごしていた生後5カ月のことだ。ある日を境に、水から有害物質が検出されたり、放射性物質を含む野菜が、出荷停止になったりした。そう、その出来事とは、東日本大震災、福島第一原発事故のことである。
会社員だった父も、都会に慣れていた母も、安心して子育てをするため、山口県の山間地域への移住を決めた。そこは人口500人、近所の人と採れた野菜を渡し合う温かい場所だった。それからだと言う。父と母が「食」に気を遣い始めたのは。父は一から農業を学び、農家を始めた。母も、父を手伝うようになった。東日本大震災で、僕達家族の人生は、180度変わったのである。
人は、食べ物抜きには生きていけない。ただ、僕達は、食べ物は当たり前のように毎日手に入るものだと信じている。実際そんな簡単なものではない。一食一食に大勢の人達が関わっていて、何かあると、今までそこにあった一食は、もうないのである。こんな体験をした僕だからこそ、「食」に関して考えたことがある。
まず一つめは、農業の大切さである。父は、雨の日や暑い夏でも、毎日畑で作業している。その姿は、本当に大変そうだ。しかし、農業は人の「 生命(いのち)」を育む大切な仕事だと思う。日本の食料自給率は低く、多くを輸入に頼っている。世界の人口が増え続け、気候変動が進行する中、今までどおり食料を輸入することができるのか。それは難しくなってくるだろう。これから農業をもっと活性化し、少しでも多くの食料を自国でまかなえるようにしなければならない。しかし、現実には生産者の年齢層は高く、跡つぎがいないという声を耳にする。僕は、幼い頃から野菜が育つのを見てきた。自分で植えた苗の成長は、とてもうれしいものだった。そこで、子ども達や若者が、農業を体験する機会をもっと増やしてはどうだろうか。食べ物を生産する難しさや喜びを身をもって知るだけでも、農業の大切さに気づくきっかけになる。そして、生産者への感謝や応援したいという気持ちが、地産地消の促進につながるのではないだろうか。
一方で、食品ロスの問題もある。日本では大量の食品が、毎日廃棄されている。給食でも、注ぎきれずに余ってしまうことがある。そんなとき、僕はおかわりをして、食缶を必ず空にする。父や近所の方の一生懸命な姿を思うと、無駄にはできないからだ。先ほどの「農業体験」は食品ロスの削減にも役立つと思う。外国では、紛争や貧困などで、一日一食さえ満足に食べられない人も大勢いる。食品ロスの問題を考えることは、世界中の人々の幸せを考えることでもある。
そして、もう一つは、「食」を通じての団らんの大切さである。現代の食事は、短時間で済むようになった。ほとんどの家が共働きで、みんな忙しい。だからこそ、晩ご飯のひととき、「食」を楽しむ時間が必要なのではないかと思う。食べながら、生産者の苦労や遠い国の人々に思いをはせること、それだけでも「食」をめぐる問題の解決に向けて、小さな一歩になるのではないだろうか。
14年前の出来事がなかったら、僕は「食」についてこんなに関心をもたず、食べ物は当たり前のように手に入るものだと考えていただろう。でも今は、「食」が手に入るまでの苦労やありがたさを知っている。そして、これからの「食」は、僕達若者が守っていかなければならないと気づくことができた。未来の僕達、生まれてくる子ども達、世界中の人達のために、僕達は、「食」と向き合うべきだ。大きな行動でなくても、小さなみんなの「関心」は、生産者、農業の支えとなる。そうすれば、「今ここにある食卓」だけでなく、「未来のどこの食卓」にも新鮮な食材と笑顔があふれていると信じている。
山口県立高森みどり中学校 3年 須田 青慈
人は、生まれて間もない頃の記憶をもっていない。しかし、そんな時期に、僕には人生を変えるような出来事があった。千葉県松戸市で過ごしていた生後5カ月のことだ。ある日を境に、水から有害物質が検出されたり、放射性物質を含む野菜が、出荷停止になったりした。そう、その出来事とは、東日本大震災、福島第一原発事故のことである。
会社員だった父も、都会に慣れていた母も、安心して子育てをするため、山口県の山間地域への移住を決めた。そこは人口500人、近所の人と採れた野菜を渡し合う温かい場所だった。それからだと言う。父と母が「食」に気を遣い始めたのは。父は一から農業を学び、農家を始めた。母も、父を手伝うようになった。東日本大震災で、僕達家族の人生は、180度変わったのである。
人は、食べ物抜きには生きていけない。ただ、僕達は、食べ物は当たり前のように毎日手に入るものだと信じている。実際そんな簡単なものではない。一食一食に大勢の人達が関わっていて、何かあると、今までそこにあった一食は、もうないのである。こんな体験をした僕だからこそ、「食」に関して考えたことがある。
まず一つめは、農業の大切さである。父は、雨の日や暑い夏でも、毎日畑で作業している。その姿は、本当に大変そうだ。しかし、農業は人の「 生命(いのち)」を育む大切な仕事だと思う。日本の食料自給率は低く、多くを輸入に頼っている。世界の人口が増え続け、気候変動が進行する中、今までどおり食料を輸入することができるのか。それは難しくなってくるだろう。これから農業をもっと活性化し、少しでも多くの食料を自国でまかなえるようにしなければならない。しかし、現実には生産者の年齢層は高く、跡つぎがいないという声を耳にする。僕は、幼い頃から野菜が育つのを見てきた。自分で植えた苗の成長は、とてもうれしいものだった。そこで、子ども達や若者が、農業を体験する機会をもっと増やしてはどうだろうか。食べ物を生産する難しさや喜びを身をもって知るだけでも、農業の大切さに気づくきっかけになる。そして、生産者への感謝や応援したいという気持ちが、地産地消の促進につながるのではないだろうか。
一方で、食品ロスの問題もある。日本では大量の食品が、毎日廃棄されている。給食でも、注ぎきれずに余ってしまうことがある。そんなとき、僕はおかわりをして、食缶を必ず空にする。父や近所の方の一生懸命な姿を思うと、無駄にはできないからだ。先ほどの「農業体験」は食品ロスの削減にも役立つと思う。外国では、紛争や貧困などで、一日一食さえ満足に食べられない人も大勢いる。食品ロスの問題を考えることは、世界中の人々の幸せを考えることでもある。
そして、もう一つは、「食」を通じての団らんの大切さである。現代の食事は、短時間で済むようになった。ほとんどの家が共働きで、みんな忙しい。だからこそ、晩ご飯のひととき、「食」を楽しむ時間が必要なのではないかと思う。食べながら、生産者の苦労や遠い国の人々に思いをはせること、それだけでも「食」をめぐる問題の解決に向けて、小さな一歩になるのではないだろうか。
14年前の出来事がなかったら、僕は「食」についてこんなに関心をもたず、食べ物は当たり前のように手に入るものだと考えていただろう。でも今は、「食」が手に入るまでの苦労やありがたさを知っている。そして、これからの「食」は、僕達若者が守っていかなければならないと気づくことができた。未来の僕達、生まれてくる子ども達、世界中の人達のために、僕達は、「食」と向き合うべきだ。大きな行動でなくても、小さなみんなの「関心」は、生産者、農業の支えとなる。そうすれば、「今ここにある食卓」だけでなく、「未来のどこの食卓」にも新鮮な食材と笑顔があふれていると信じている。
令和7年度少年の主張コンクール発表作文紹介 優秀(県民会議会長賞)
2025/10/03
「言葉の強さ」
下松市立久保中学校 3年 三浦 仁太
皆さんには、両親はいますか。私の両親は、私が小学四年生の頃に離婚しました。今は、父と兄と三人で暮らしています。今時、親が離婚するのは珍しくありません。しかし、小学生の私にとって、それは受けいれがたいことでした。いえ、信じられませんでした。「これは何かの間違いだ。そうだ、きっとこれはドッキリなんだ。」とずっと心の中で唱えていました。そうしないと、自分が壊れてしまいそうで怖かったからです。しかし、普段は全く泣かない兄が泣いているのを見て、「あっ、これは間違いでもドッキリでもないんだ。本当なんだ。」と分かると同時に、いろいろな気持ちがあふれ出しました。両親が離婚することへの悲しみ、この家庭に生まれたことへの憎しみ、他の平和な家庭への妬みなど、全部挙げたらきりがありません。小学生の私には、この現実を受け止めることが本当に辛かったです。
母が家を出る日のことは、今でも忘れられません。母は、
「お仕事、行ってくるね。夜勤だから、明日の朝まで帰れないの。お留守番頑張ってね。」と私に言いました。母は、私が不安にならないように、嘘をついたのです。しかし私は母がもう家に帰ってこないことを知っていました。けれども、いや、だからこそ、私は笑顔で、
「いってらっしゃい。」
と言いました。その日の夜、私は分かっているにも関わらず、母が帰ってくるという僅かな希望を抱いて眠りました。しかし、朝起きても母は帰ってきていませんでした。
私は絶望しました。その日から、私は生きる光がなくなったように感じました。学校では両親の離婚について一切触れず、「いつも通り」を演じていました。少しでも自分の感情を出すと、学校のみんなを妬む気持ちが爆発してしまいそうだったからです。その頃から、私は、心の中の思いを押し殺し、上から嘘を塗りたくることが普通になってしまいました。思いを押し殺すことによる疲れやストレスさえも押し殺す、そんな無限ループにはまってしまいましたが、何も感じることはありませんでした。
ある日、学校から帰る途中、友達が不意に
「大丈夫?」
と声をかけてきました。どうやら、疲れやストレスが蓄積されすぎて表に出てしまったようです。すぐにそれらを無理やり押し殺して、「大丈夫だよ」と言おうとする前に、彼は、「辛いことがあったら何でも相談してね。だって僕たち、友達でしょ。」
と言いました。彼は何気なく言ったのかもしれません。でも、私の心には一筋の光が差し込み、それまでのもやもやがパアッと晴れたように感じました。本当の思いをひた隠しにしていた私の心は、実は誰かの優しい一言を待ち望んでいたのだと気付きました。
その日から私は、自分の気持ちに嘘をつくことや、人を妬むことを止めました。私は再び、より多くの友達と笑顔で会話することができるようになりました。あのときの彼の一言が、私にもう一度、生きる光を灯してくれたのです。
私は、今、生徒会長を務めています。友達は「仁太、仁太」と気軽に声をかけてくれます。「仁太ならできるじゃろー」とも言ってくれます。こうして、今、私が楽しく生活できているのも、全ては彼がかけてくれた言葉のおかげです。次は私の番です。彼が私を救ってくれたように、今度は私が、何かに困ったり悩んだりしている人を救いたいです。そして、伝えたいです。「自分の気持ちに嘘をつかないで。苦しいときは苦しいと言ったほうがいいよ。私があなたの思いを受け止めるから。」と。
下松市立久保中学校 3年 三浦 仁太
皆さんには、両親はいますか。私の両親は、私が小学四年生の頃に離婚しました。今は、父と兄と三人で暮らしています。今時、親が離婚するのは珍しくありません。しかし、小学生の私にとって、それは受けいれがたいことでした。いえ、信じられませんでした。「これは何かの間違いだ。そうだ、きっとこれはドッキリなんだ。」とずっと心の中で唱えていました。そうしないと、自分が壊れてしまいそうで怖かったからです。しかし、普段は全く泣かない兄が泣いているのを見て、「あっ、これは間違いでもドッキリでもないんだ。本当なんだ。」と分かると同時に、いろいろな気持ちがあふれ出しました。両親が離婚することへの悲しみ、この家庭に生まれたことへの憎しみ、他の平和な家庭への妬みなど、全部挙げたらきりがありません。小学生の私には、この現実を受け止めることが本当に辛かったです。
母が家を出る日のことは、今でも忘れられません。母は、
「お仕事、行ってくるね。夜勤だから、明日の朝まで帰れないの。お留守番頑張ってね。」と私に言いました。母は、私が不安にならないように、嘘をついたのです。しかし私は母がもう家に帰ってこないことを知っていました。けれども、いや、だからこそ、私は笑顔で、
「いってらっしゃい。」
と言いました。その日の夜、私は分かっているにも関わらず、母が帰ってくるという僅かな希望を抱いて眠りました。しかし、朝起きても母は帰ってきていませんでした。
私は絶望しました。その日から、私は生きる光がなくなったように感じました。学校では両親の離婚について一切触れず、「いつも通り」を演じていました。少しでも自分の感情を出すと、学校のみんなを妬む気持ちが爆発してしまいそうだったからです。その頃から、私は、心の中の思いを押し殺し、上から嘘を塗りたくることが普通になってしまいました。思いを押し殺すことによる疲れやストレスさえも押し殺す、そんな無限ループにはまってしまいましたが、何も感じることはありませんでした。
ある日、学校から帰る途中、友達が不意に
「大丈夫?」
と声をかけてきました。どうやら、疲れやストレスが蓄積されすぎて表に出てしまったようです。すぐにそれらを無理やり押し殺して、「大丈夫だよ」と言おうとする前に、彼は、「辛いことがあったら何でも相談してね。だって僕たち、友達でしょ。」
と言いました。彼は何気なく言ったのかもしれません。でも、私の心には一筋の光が差し込み、それまでのもやもやがパアッと晴れたように感じました。本当の思いをひた隠しにしていた私の心は、実は誰かの優しい一言を待ち望んでいたのだと気付きました。
その日から私は、自分の気持ちに嘘をつくことや、人を妬むことを止めました。私は再び、より多くの友達と笑顔で会話することができるようになりました。あのときの彼の一言が、私にもう一度、生きる光を灯してくれたのです。
私は、今、生徒会長を務めています。友達は「仁太、仁太」と気軽に声をかけてくれます。「仁太ならできるじゃろー」とも言ってくれます。こうして、今、私が楽しく生活できているのも、全ては彼がかけてくれた言葉のおかげです。次は私の番です。彼が私を救ってくれたように、今度は私が、何かに困ったり悩んだりしている人を救いたいです。そして、伝えたいです。「自分の気持ちに嘘をつかないで。苦しいときは苦しいと言ったほうがいいよ。私があなたの思いを受け止めるから。」と。
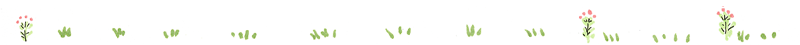
やまぐち子育て連盟 http://yamaguchi-kosodate.net